少年技師ハンドブック
「少年技師ハンドブック」は第2次世界大戦前に誠文堂から刊行されていた工作本のシリーズ。戦後には同じく誠文堂新光社から「少年技師ハンドブック」や「少年技師のハンドブック」が出版されている。両シリーズで同名の書籍もあるけれども、著者・内容とも異なっているものもある。
少年技師ハンドブック
少年技師ハンドブックは以下の紹介する20編からなるシリーズものである。ただ、第1編の巻末広告を見ると、12編までしか掲載されておらず、そのあとの表記には全13編のシリーズであると記されているので、計画当初から冊数は変更になったものと推測される。本は新書版サイズでしぼのある赤色の人造皮革の装丁で、表面には少年技師のレリーフ像がある。
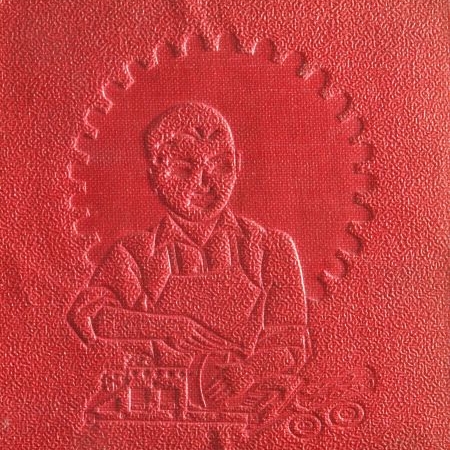
書名は背表紙のみに記載されている。発売時には、本ごとに異なったデザインのカバーがあり、カバーには署名や著者名も記載されているが、中古で残っているものは裸本も多い。
シリーズ物ではあるけれども、出版社からの趣旨説明はない。第1編には著者前書きがあり、これが、出版社からの趣旨説明に変わるようなものであると思うので、以下紹介する。
はしがき
小学校、中学校、大学と云う順にその学生の勉強ぶりを見てみる。すると一般は意外にも非常識きわまる失敗をやっている。日本の科学文明がその輸入当時に書物によって入って来たものだから、いつか科学を机の上にのみ取扱うことになていた。これがそもそも日本の文明が普遍的に進歩しない証拠である。で科学知識の実際化と云う事を常に現代に於ける日本の急務と考え、及ばず乍らこの小さい私も同志の先輩と手をとってその方針を進めつつある次第であるが、常に科学の実際化は「イタヅラ」よりとのみお勧めしている通り、各自の欲するままに、或いは自動車が作ってみたい。或いは電気機関車が作ってみたい、または大分植物を採集したからこれをもっともっと集めてみようと云うように、趣味から趣味を追う処に無理ならぬ自然の欲求を生じ、これ同時に論なく科学を完全に親しむことになるので、ことさら机上にその実際化を叫ぶのは、寧ろ効果に於いて疑われるものと信じている。真剣なる「イタヅラ」!熱のあるところに向かっての「イタヅラ」! これが知をもって立つ地球上の動物即ち人間に必然的の分子と云い得る。あの無茶苦茶に多くの発明特許をもつエヂソン、また今年が電灯五十年祭として世界の記念の中心となったエヂソン! エヂソンは「真面目なるイタヅラ者」としての大先輩です。そして八十歳を超えた現在いまだにイタヅラを--それこそ諸君位の年齢の時にやったイタヅラを少しも変えずに同じ方針でやっている。私は諸君にその進むべき方向は強いない。ただ、己が長所即ち熱を出すことを少しも苦にしない自分のすきな道、それをより以上より多く、延ばされんことを何に置いても第一にお願いするのみです。
昭和四年の秋
四谷の個人研究所にて
本間清人述
以下にシリーズ各編のタイトルなどの情報を示す。タイトルの後に※マークがあるものは、国会図書館のデジタルアーカイブにあり、利用登録してあれば、Web上で閲覧できる。※※マークのものは著作権が切れているようで、登録なしで閲覧可能である(いずれも2025年8月現在)。
-
第1編;電車と電気機関車の作り方 ※
-
本間清人著:
- 第2編;科学玩具の作り方
- 本間清人著
- 第3編;モーター利用模型の作り方
- 本間清人著
- 第4編;蒸汽利用模型の作り方 ※
- 山北藤一郎著:
- 第5編;家庭実用品の作り方 ※
- 本間清人著
- 第6編;電気機械の作り方
- 山北藤一郎著:
- 第7編;軍艦・汽船の作り方 ※
- 佐々木民部著:
- 第8編;飛行機航空船の作り方 ※
- 宮里良保著:
- 第9編;やさしいラヂオの作り方 鉱石より三球まで ※
- 古沢恭一郎著:
- 第10編;四球よりスーパー迄 高級ラヂオの作り方 ※
- 古沢恭一郎著:
- 第11編;カメラと映写機の作り方 ※
- 帰山教正著:
- 第12編;望遠鏡と顕微鏡の作り方
- 鈴木義之著:
- 第13編;特許の受け方と法規集
- 子供の科学編輯部 編
- 第14編;高級電気機関車の作り方
- 山北藤一郎著:
- 第15編;セメントと面白い実用品の作り方
- 横山文司著:
- 第16編;化学実験と応用品の作り方 ※
- 横山文司著:
- 第17編;彫刻と塗装 易しい工芸品の作り方
- 山田義郎著:
- 第18編;博物標本の作り方 ※
- 大町文衛著:
- 第19編;簡易木工器具の作り方
- 蒲田賢三著:
- 第20編;電気器具と電池の作り方
- 山北藤一郎著:
少年技師のハンドブック
戦後に発行されたもので判型も異なっている。戦前と同じタイトルのものもあるが、著者が違うものは内容も異なっている。
ラヂオに関する書籍の著者は戦前版では恭一郎、戦後版では匡市朗となっているが、同一人物のようである。
-
望遠鏡と顕微鏡の作り方 ※
-
田辺敏郎 著 , 昭和23
-
模型船舶の作り方 ※
-
桑原達郎 著 , 昭和24
-
模型鉄道レイアウトの作り方 ※
-
国峰孝太郎 著 , 昭和24
-
やさしいラジオの作り方 ※
-
古沢匡市郎 著 , 昭和23
-
高級ラジオの作り方 ※
-
古沢匡市郎 著 , 昭和25
-
少年電気工作 ※
-
山北藤一郎 著 , 昭和24
-
蒸気機関車の作り方 ※
-
田口武二郎 著 , 昭和24
-
電気機関車の作り方 ※
-
山北藤一郎 著 , 昭和25
以上に加えて、書籍巻末の広告によると以下の書籍も予定されていたようだが、発行した痕跡は見つけられていない。
- 少年技師の無線学 大井 脩三
- カメラの作り方 田口武二郎
- 理科教具の作り方 中谷 行義
|